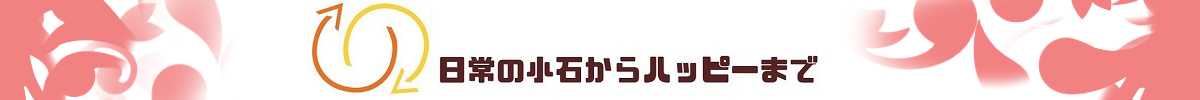今回は以下の内容で構成されています。
- 帝王切開の費用
- 帝王切開の費用の内訳
- 帝王切開の保険
帝王切開が決まって、出産費用が気になっている妊婦さんにお届けします。
帝王切開と自然分娩の費用とは?費用の差を内訳でご説明!

帝王切開と自然分娩の費用の違いを見ていくにあたって、はじめに自然分娩について明確にしておきます。
自然分娩は、経腟分娩(けいちつぶんべん)の1つになります。
この経腟分娩は、母体の産道から腟を経て赤ちゃんが生まれる分娩方法のことを言います。
ただし自然分娩の定義は、病院や産院によって異なる場合があります。
よってここでの自然分娩の定義は、経腟分娩の中で医療処置が介入しないものとして考えていきます。
それでは自然分娩の費用の内訳から確認していきましょう。
平均的な金額なので皆さんの妊婦検診を受けている病院等とは差があることは了承してください。
入院日数は、6日間とします。
2017年の自然分娩での入院料は平均112,726円とのデータがでており、料金の内訳は以下の様になります。
- 差額室料(差額ベッド代)16,580円
- 分娩料 254,180円
- 新生児管理保育料 50,621円。
さらにその他検査料は以下の様になります。
検査・薬剤料 13,124円
処置・手当料 14,503円
産科医療補償制度 15,881円
さらにその他雑費として28,085円が掛かることもあるので、合計505,759円が必要になります。
全体的な傾向を見ると自然分娩の費用は40万円から75万円くらいと考えられています。
帝王切開と自然分娩の費用の大きな違いは、入院日数が自然分娩の約2倍になることです。
しかし保険加入を考慮すると、帝王切開と自然分娩の費用の差はぐっと少なくなります。
帝王切開の手術自体の費用は、保険を計算に入れないと以下の様になります。
- 予定帝王切開の場合 20万1,400円
- 緊急帝王切開の場合 22万2,000円
以上のデータから帝王切開の費用は、自然分娩よりも10万円~20万円ほど余分にかかると考えてください。
帝王切開に強い味方!分娩費用に保険が効くことを知っておこう!

保険適用外のものと、保険適用となるものは、次のようになります。
保険適用外
- 帝王切開介助料
- 分娩処置料
- 各種検査料
- 新生児介助料
- 分娩セット
- オムツ代等
- 食事代
保険適用
- 手術料(手技料+薬剤等)
- 処置料
- 薬剤料
- 麻酔料
- 検診料
- 入院料
保険適用時の自己負担は3割です。
費用の個人差は、麻酔や入院日数などに生じます。
麻酔は腰椎麻酔と硬膜外麻酔の2種類の麻酔を組み合わせる場合と、腰椎麻酔のみ使用される場合があります。また手術状況によって全身麻酔をするケースもあります。
尚出産育児一時金の支給と高額療養費制度がありますので、費用面では安心して出産できます。
出産育児一時金の支給は出産方法問わず支給条件を満たしていれば、子どもひとりにつき42万円支給されます。
詳細は厚生労働省の出産育児一時金の支給額・支払方法についてのページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
帝王切開の医療費が1か月で上限額を超えた時は、超過分を支給する高額療養費制度の対象となります。
帝王切開が決まっている場合は、入院前に限度額適用認定証の申請をしておきましょう。
限度額適用認定証は、請求される医療費が高額療養費制度の自己負担限度額までとなるものです。
限度額適用認定証はどこで取得?
限度額適用認定証は、各健康保険の窓口に申請をして発行してもらうことができます。
まとめ

帝王切開は自然分娩の費用よりも多くかかりますが、保険適用となるもの、出産育児一時金の支給、高額療養費制度などがありますので事前に詳細を確認しておきましょう。