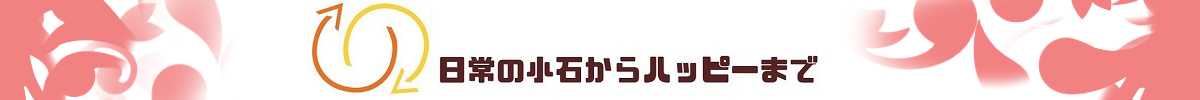「秋ナスは嫁に食わすな」ということわざを知っていますか?
優しさからきた言葉なのでしょうか、意地悪で出た言葉なのでしょうか。
とはいえ、この言葉だけでは真意がわからないですよね。
- なぜ秋ナスは嫁に食べさせてはいけないのか教えて
- どんな栄養価や効能がナスにはあるの?
- ナスに関連したことわざが知りたい
今回この記事では、「秋ナスは嫁に食わすな」ということわざを紐解いていきます。
この記事を読むとどんな意味合いがあってのことわざなのかがわかりますよ。
参考にお読みください。
目次
秋ナスはなぜに嫁に食べさせるなと言われたのか?秋ナスは特別なの?

ナスの旬は初夏から秋にかけてです。
夏に穫れるナスはミズミズしいのが特徴で、秋に穫れるナスは種が少なく実は締まっています。
そこで秋ナスは嫁に食わすなということわざの解釈には、4つの解釈があります。
・1つ目の解釈
ナスは体を冷やす食べ物だから、これから赤ちゃんを産んでもらう嫁には体を冷やしてほしくないという理由です。
・2つ目の解釈
夏に穫れるナスより、秋に穫れるナスの方がアミノ酸や糖といったうま味成分が多いのです。
そんな美味しい秋ナスを嫁に食べさせるのもったいないという意地悪な説。
・3つ目の解釈
秋ナスには種が少ないので、子宝に恵まれないという説です。
・4つ目の解釈
嫁を夜の目と書いて、ネズミのことを指します。
美味しい秋ナスをネズミに食べられないようにしなさいといった説。
ナスの栄養価や効能にはどんなものがあるのか?ナスの種類は

ナスには、皮の色素にナスニンと呼ばれるポリフェノールが含まれています。(アントシアニンの1種)
アントシアニン系のポリフェノールの中では、ナスニンの抗酸化力が最も強いのです。
ですからナスは皮ごと食するのが効果的。
そしてナスの皮や果肉部分には、クロロゲンというポリフェノールも多く含まれています。
このクロロゲンには下記の効果があるのです。
- 脂質分解を早める作用
- 血液をサラサラにする作用
- 副交感神経を刺激して気分を落ち着かせる作用
その他にオスチンと呼ばれる植物性タンパク質が含まれています。
このオスチンには体内の糖代謝を整える作用があり、メタボ予防にも役立つのです。
ナスの種類
| 名前 | 特徴 | 食べ方 |
| 大長ナス | 40~60cm長のナス。皮は固めだが、果肉が柔らかい。炒め物や揚げ物では油を吸いやすい。 | 加熱 九州では焼きナスにするのが一般的。 |
| 長ナス | 20cm前後の長さで、ナスの総称。同じ大きさの輪切りが多くとれる。肉質が柔らかい。 | 加熱 煮物や揚げ浸し、焼きナスに向いている。 |
| 丸ナス | 丸くて大きいナス。肉質が硬く締まっていて加熱しても煮崩れにくい。京都の賀茂ナスも丸ナスの一種 | 加熱 田楽やトマト煮に向いている。 |
| 米ナス | 米国のブラックビューティーという品種を日本で改良したものと言われる。表皮が濃い紫でヘタは緑色なのが特徴。繊維がしっかりしていて煮崩れしにくい。 | 加熱 田楽やステーキ、ラタトーユの煮込みに向いている。 |
| ロッサビアンゴ | イタリア原産の紫と白が混じったナス。直径10cmほどの肉厚でアクが少なくクリーミーな味わい。 | 加熱 チーズやトマトソースと共にグラタンや塩コショウしてソテーにも向いている。 |
| ホワイトスレンダー | 白長ナスの1種。アクが強く切ると断面が変色しやすい。加熱すると皮も果肉も柔らかく、料理を白く仕上げたいときに向いている。 | 加熱 田楽やステーキ・和え物などどんな料理にも合う。 |
| 太刀緑 | 青長ナスの1種で、クロロゲンが豊富。やや硬めだが、果肉は濃厚なうまみがある。 | 加熱 焼きナスやカレー、グラタンに向いている。 |
| 千両ナス | 最も一般的な長卵形のナスで、濃黒紫色つやがある。果肉、皮ともに柔らかく生食もできる。 | 加熱(生食) 漬物や煮物、煮浸しなど幅広い料理に向いている。 |
| 名前 | 特徴 | 食べ方 |
| サラダナス | 生で食べられるように品種改良したナスで、アクは少なく甘みがある。 | 生食 サラダや和え物、浅漬に向いている。 |
| 赤ナス | 熊本の伝統野菜で、アクが少なく果肉はふんわりと柔らかくジューシー。 | 生食 焼きナスにすると甘みがあり、とろけるような食感。 |
| 小ナス | 重さ10~20gの丸型のナス。山形の民田ナスやそれを品種改良した出羽小ナスがある。 | 生食 漬物や煮浸しに向いている。 |
| 水ナス | 大阪の泉州が特産。水分が多く皮も果肉も柔らかく、アクはは少ないのが特徴。 | 生食 そのまま手で割ってサラダに使用。 |
・ナスの肉味噌炒め
・ナスのワサビ漬け
・豚バラナスのスタミナ炒め
・ナスのみぞれ炒め
・ナスのラタトーユ
ナスを使ったことわざ・慣用句の意味を解説

ナスを使ったことわざや慣用句を説明していきます。
単にナスを使ったことわざといっても思い浮かばなくても、例を上げると聞いたことがあることわざばかりです。
・一富士二鷹三茄子(いちふじにたかさんなすび)
初夢に見ると縁起が良いとされるものをめでたい順番に並べた句です。
・瓜の蔓に茄子はならぬ(うりのつるになすびはならぬ)
瓜の蔓に茄子はならぬとは、平凡な親から非凡な子は生まれないことのたとえ。
・親の意見と茄子の花は千に一つも無駄はない(おやのいけんとなすびのはなはせんにひとつもむだなない)
ナスの花はすべて実って一つの無駄花がないように、親が子を思っていう意見はすべて大事なことばかりであること。
・ナスの豊作は稲の豊作(なすのほうさくはいねのほうさく)
ナスが順調に育つ気候であれば稲にも適した天候であること。
・初ナスの皮が厚ければ米は不作(はつなすのかわがあつければこめのふさく)
ナスは米と同様で、成長のタイミングで水分を多く必要とし、水が不足すると皮が厚くなるため干ばつ気味であることの警告。
・ナスの実がかたくておいしいときは凶作(なすのみがかたくておいしいときはきょうさく)
水分が足りていない可能性の示唆です。
まとめ:いろいろな意味合いがある秋ナスを積極的に摂って健康的に!

本当はどんな意味合いで言われたかは定かでありません。
ナスを調べるといろいろな料理に活用できるし、健康にも役立つ食品です。
疑問に思ったことは積極的に調べて、深い意味合いを考えるのも楽しいですね。